みなさんこんにちは
こっこ先生のあそびばへようこそ!
9月に入り、少しずつ秋を感じられるようになってきました。
今年も十五夜が近づいてきましたね。
2021年の十五夜は9月21日(火)です。
保育園や幼稚園でも、月の話題が多くなってくるころではないでしょうか。
今回は、十五夜にちなんだお月見や月に関するおすすめ絵本の紹介です。私、こっこ先生が実際に子どもたちと読んで、印象に残っている絵本たちを集めました。
年齢別に紹介しているので、対象の子どもに合った絵本を探す際にぜひ参考にしてみてくださいね。
おすすめ月の絵本

月の絵本を探すとたくさんの絵本がヒットします。
今回ご紹介する絵本は私、こっこ先生が子どもたちと読んで「これはいい絵本だな」と思った本たちです。
子どもたちが笑顔になったり、子どもたちの心に響いたり・・・
きれいで不思議な月のお話を子どもたちと楽しんでみてくださいね。
0,1,2歳児におすすめの絵本
0,1,2歳児に合った月の絵本を探す時には、お話の主役が「月」だと分かりやすいものを選ぶようにしましょう。
その本の主役を示す方法は、絵だったり言葉だったりと、絵本によって表現の仕方は異なります。
みなさんもご存知の通り、0,1,2歳児は言葉として聞くよりも、目で見た情報の方が理解しやすいという特性があります。
そういった観点からも、絵を見て「あ、おつきさまのお話だ」と分かる絵本を探すといいでしょう。
中には、周りに描かれている絵が細かく、にぎやかな絵本もあります。
しかし、そういった絵本は0,1,2歳児の「絵から読み取るハードル」を高くしてしまう恐れがあるので、注意して選びましょう。
シンプルな絵と歌うような言葉で赤ちゃんにっこり
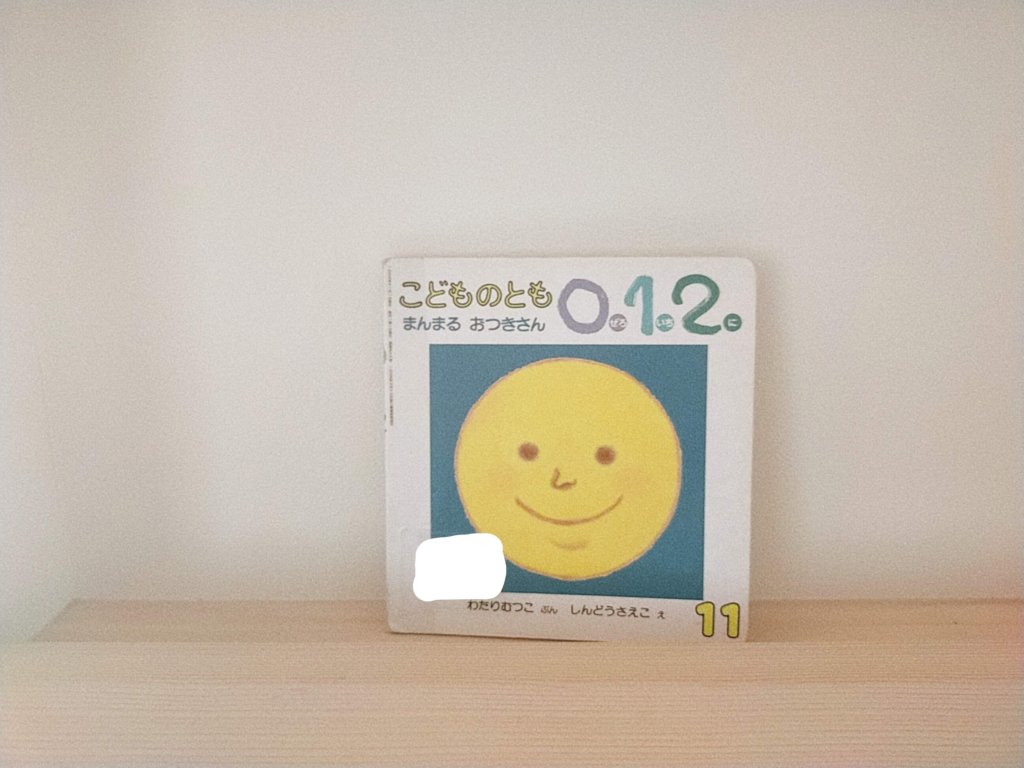
わたりむつこ ぶん/しんどうさえこ え(福音館書店)
この絵本は初めから終わりまで、一貫してお月様の絵が右ページに集約され、左ページにはお話を彩る動物たちが登場します。
このコントラストがとても気持ちのよい絵本です。
無駄のない絵と、つい節をつけて歌いたくなるようなシンプルで楽しい言葉に子どもたちも釘付けになります。
まんまるお月さまっておいしそう!
まんまるのお月さまを見ていたら、なんだかいろんな食べ物に見えてくる!
そんな子どもの想像力が楽しいお話になったのがこの絵本です。
この絵本を読んだ日にはぜひ保護者の方へもお知らせくださいね。
夜に家族でお月さまを見るよいきっかけになるかもしれません。
そこにいる安心感
園やクラスにこの絵本を置いている方も多いのではないでしょうか。
絵本は絵を見るだけで楽しめなくてはいけない、そのような絵が描かれている絵本が子どもに与えたい絵本だ。と聞いたことがあります。
この絵本はまさにそれです。絵を見るだけでお話の流れが分かります。まるで美術館の絵画を見ているようで、月夜の情景にどっぷり浸れる絵本です。
そこにやさしく柔らかい言葉が乗り、子どもたちの心にそっと届くことでしょう。
雲に隠れてもお月さまは空に居続ける
という対象の永続性を獲得した6か月ころからは、「あーいたいた」という安心感をもつことができるでしょう。
裏表紙のベーっと舌を出したお月様の真似をする子がいるかしら?
『おつきさまこんばんは』パパの大きな愛情を感じられる一冊
『はらぺこあおむし』でおなじみのエリック・カールさんの絵本です。
満月の大きさや幻想的な夜空がしっかりと描かれています。
「パパ、お月さまとって!」という娘の要望に父親が応えようとするストーリー。
遠い月の世界とながーいはしごでつながるページは圧巻です。
絵本が好きな2歳児クラスなら読めるかな、と思いここで紹介しました。もちろん、3,4,5歳児の子どもたちにもぜひ読んでほしい一冊です。
『パパ、お月さまとって!』3,4,5歳児におすすめの絵本
3歳以上児にはお話の世界をしっかり楽しめるような絵本をおすすめします。
決してお話の長さだけではなく、話の内容をじっくり吟味して良い絵本を選びたいですね。
科学的な視点を取り入れた絵本もいいですね。
月の満ち欠けに気付いたら
3,4,5歳児になってくると、月の形が日によって違うことに気付きます。十五夜はそんな科学の芽を育てるのにもぴったりな行事です。
この絵本は細い月やまんまる満月、いろいろな形の月が出てきます。
夜には月の観察をしたくなるかもしれませんね。
『おつきさまこっちむいて』縦長の形を存分に活かしたストーリー
この絵本はパッと目をひく35×13cmの縦長の絵本です。
お月さまが下を見ると、池に映ったもう一人のお月さまを見付けます。
つきのぼうやに連れてきてほしい、と頼むところからお話は始まります。
つきのぼうやが空からふわふわと降りてくる様子が丁寧にかかれており、お話の世界に入り込んで楽しめますよ。
『つきのぼうや』お月見会で見るときにおすすめ


大勢の子どもたちが集まるお月見会などでは、どの場所からでも見やすい大型の絵本や紙芝居、パネルシアターなどがおすすめです。
いつもとは違う雰囲気で見るお話も行事ならではですね。
たまには紙芝居でもいかが?
分かりやすいストーリーなので、0,1,2歳児クラスの子どもたちも一緒に楽しめる紙芝居です。
行事では、幅広い年齢の子どもが楽しめるお話を選ぶことも必要ですね。
紙芝居はぜひ紙芝居の舞台を使って、あの枠からお話が飛び出してくるようなわくわく感を子どもたちにもってほしいですね。
『もりのおつきみ』千世 繭子 脚本/さとう あや 絵(童心社)
おなじみの絵本が大きくなったよ
上でもご紹介した『パパ、お月さまとって!』には大型の絵本もあります。
大型絵本は保育者2人で扱うようにしましょう。
可能であれば、さらにもう一人が読み手になるとより落ち着いて読み聞かせが行えると思います。
さいごに
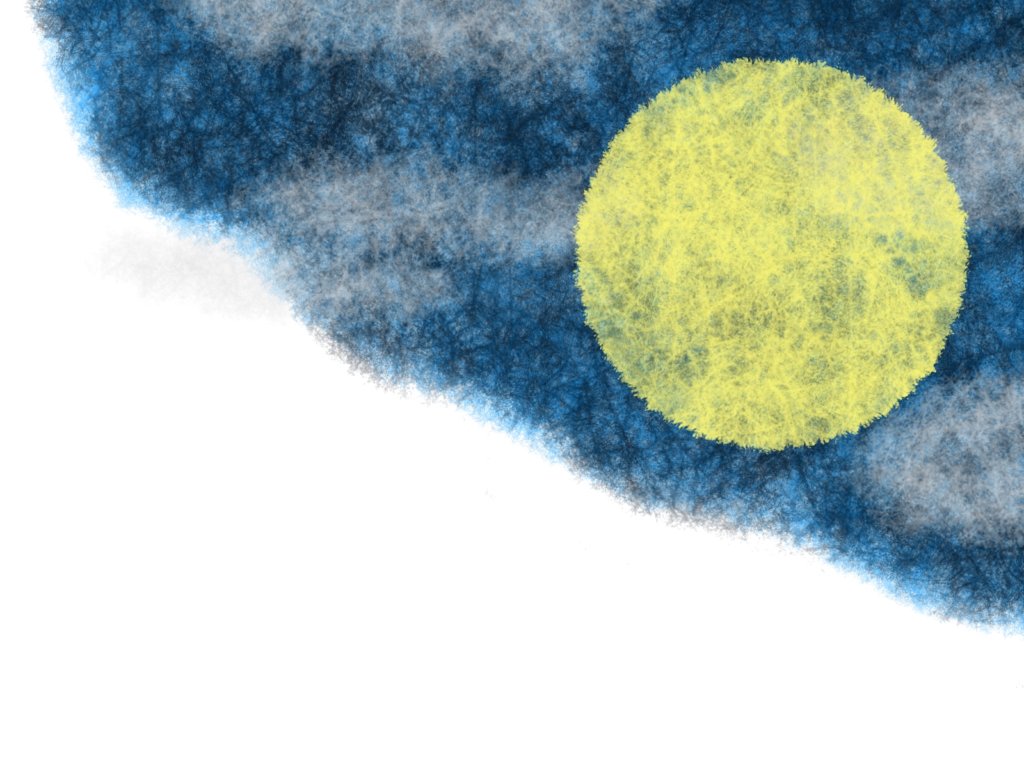
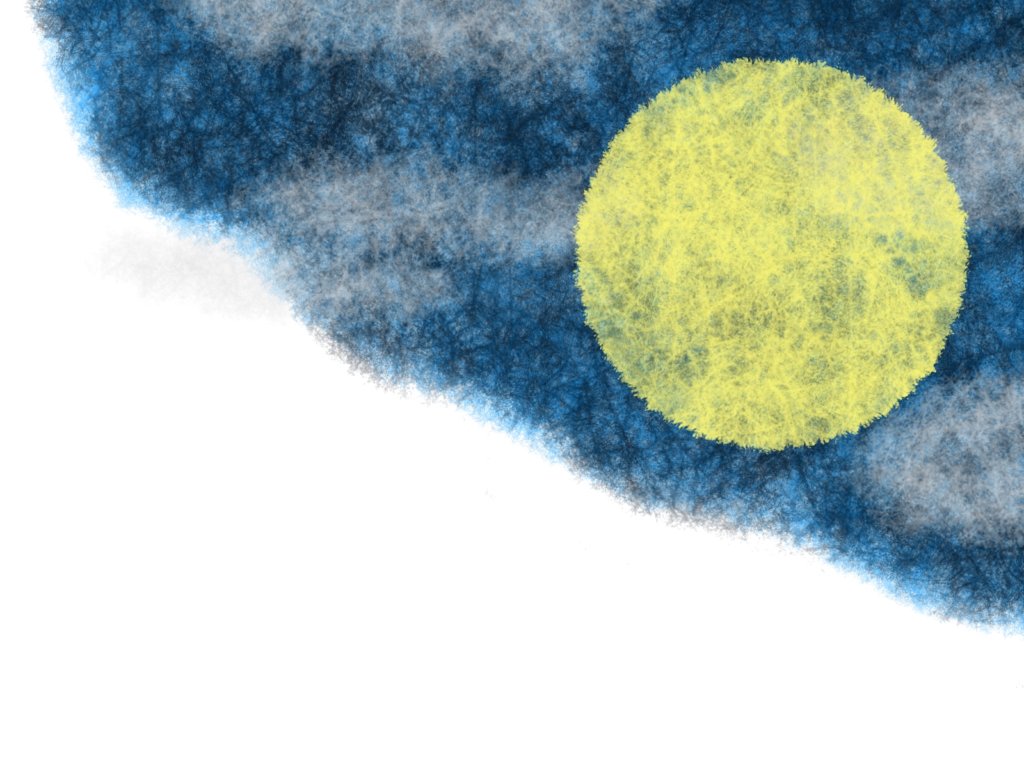
夜、少しだけ夜更かしをして月を見るって、子ども心にとてもわくわくした覚えがあります。
そして月あかりの下で家族とお話したりお月見団子を食べたり・・・
日本の素敵な文化ですよね。
私たち保育者は子どもたちと一緒に月を見ることはできませんが、ぜひ月に思いを馳せながらわくわくした気持ちを子どもたちと味わってくださいね。
その一つの方法として絵本をうまく活用していきましょう。
それではみなさん
さよならあんころもち
またきなこ♪
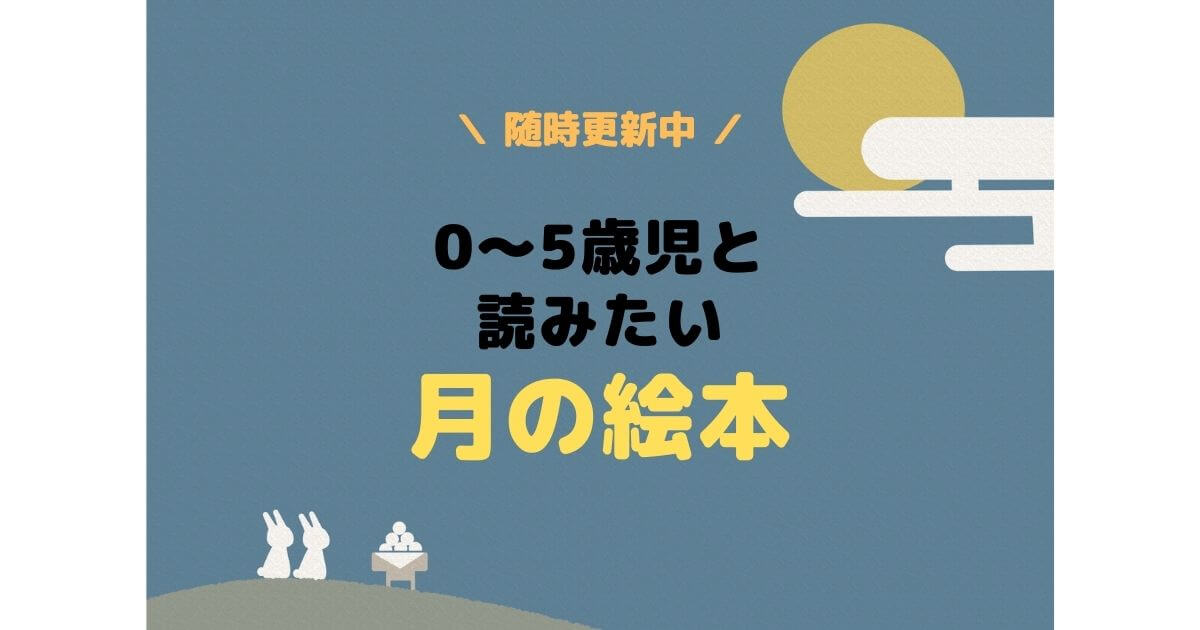
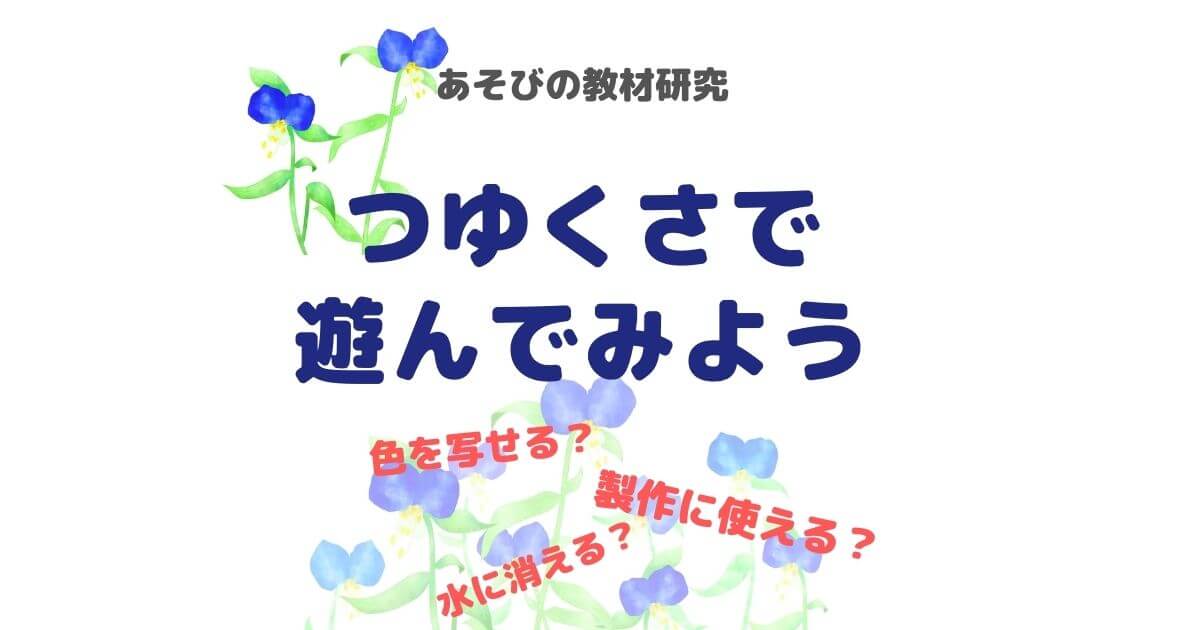

コメント