みなさん、こんにちは
『こっこ先生のあそびば』へようこそ!
朝晩が涼しくなってきましたね。
幼稚園・保育園・こども園などでは「運動会」シーズンでしょうか。
今回は特別支援教育の視点から、「運動会」に使えるおすすめの支援がありますので、ご紹介しますね!
安心して「運動会」を迎えるために。
運動会当日の雰囲気って、いつもの園の様子とは違いますよね。
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”senpai-speech.png” name=”先輩先生”]子どもたち、こんなことを思っているかも![/speech_bubble]
おうちの人もなんだか朝から「今日は頑張ってね!!」とプレッシャーを掛けてくるし。
園に行ったら、先生もなんか気合入っちゃってるし。
なんか、人が周りにいっぱいだし、なにこれ~??
こんなちょっとした環境の変化(物的も人的も)を敏感に感じ取る子どもは、ちょっと気後れしてしまったり、不安になってしまったりする可能性があるのです。
[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”kokko.png” name=”こっこ先生”]普段の力を発揮できるような支援はないんでしょうか?[/speech_bubble]
「写真」を使った手立て
これは、特に初めての環境や環境の変化が苦手な子どもに効果的な支援です。
昨年の運動会の写真で結構ですので用意してみましょう。
当日の園庭やお客さんがたくさんいる風景。
また、その中で体操をしたり、リレーをしたりしている写真を用意しておいて事前に見せておくといいでしょう。
こうすることで、今まで漠然としていた「うんどうかい」が子どもの中でより具体的になっていきますね。
[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”kokko.png” name=”こっこ先生”]先輩先生、支援を要する子どもに写真を見せていたら、他の子どももきて「見せて見せて」と大騒ぎに・・・(・・;)[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”senpai-speech.png” name=”先輩先生”]もちろん、支援を要する子どもだけでなく、他の子どもにも見せてあげてもいいのよ![/speech_bubble]
支援児への支援が、他の子どもにとっても分かりやすく安心して過ごせる園生活へと繋がっていきます!
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”senpai-speech.png” name=”先輩先生”]みんなで見た後には、掲示物として貼っておいて、いつでもその雰囲気を感じられる環境づくりをしてもいいでしょう。[/speech_bubble]
できる準備は子どもと一緒に!
こっこ先生は様々な園を経験しましたが、行事の事前準備に子どもたちがどこまでかかわるか、って園によっていろいろだなぁ、と感じています。
発達段階や携われるものによりますが、できることなら、
少しでも子どもが手を加えたり、
前日に道具を運んだり、数や色を揃えたり、
自分の衣装に破れているところがないかチェックしたり・・・
こんなこをとしていくうちに、先生側が「明日は運動会よ!みんな気合入れて!」なんて言葉掛けをしなくても、
子どもたちが自発的に「明日は運動会なんだ!」「わくわくするね!」「ボクはちょっとドキドキしてきた」などという思いを持つことができますね!
[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”kokko.png” name=”こっこ先生”]こういう経験が「内発的な動機付け」となり、子どもたちのその後の活動にいきて来ると思います[/speech_bubble]
あってよかった!「運動会当日」の支援グッズ!
ここからは、運動会当日にも使える支援グッズを紹介しますね!
[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”kokko.png” name=”こっこ先生”]よし!当日に向けて張り切って作るぞ~ヽ(^o^)丿[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”senpai-speech.png” name=”先輩先生”]こっこ先生!当日いきなり見せても子どもたちは戸惑うと思うよ💦[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”kokko.png” name=”こっこ先生”]はっ!そうでした(^^;)これも事前に見せておくことが大切ですね![/speech_bubble]
運動会プログラムの視覚化グッズ!
[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”kokko.png” name=”こっこ先生”]プログラムの視覚化??なんだか難しそう・・・[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”senpai-speech.png” name=”先輩先生”]そんなことはないわよ(^^)当日の子どもたちの動きを文字や絵にかいて示すということなの![/speech_bubble]
これ、こっこ先生が先輩先生から教わって毎年作っていた支援グッズなんです。
たとえば・・・
運動会のプログラム(種目)ってありますよね。
そのプログラムの順番を書いていきます⇩
自分たちの出るプログラムは太字や色を付けて。
また、自分たちの出ないプログラムでは、「どう過ごすのか」を簡単に書いておくものいいですね。
特に人手の少ない園では、担任が準備をするので、子どもたちのところにずっとついておくことが難しい時がありますからね。
また、実際に練習の時に撮っておいた自分たちがしている写真を、「開会式」や「体操」などの文字の横に貼っておいてもいいでしょう。
「かいかいしき」という言葉でピンとこない子どももいるかもしれませんからね。
絵が得意な先生はご自分の絵でもいいですね!
支援グッズに自分らしさがでます(*’ω’*)
[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”kokko.png” name=”こっこ先生”]子どもたちの目に触れやすい「待機場所」や「クラス」にはっておくといいですね![/speech_bubble]
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”senpai-speech.png” name=”先輩先生”]貼りだす場所は周りの先生に事前に相談してね。場所がなければ、幼児椅子の背もたれや幼児机なんかにも貼れるよ![/speech_bubble]
発達年齢に応じた手立てをしよう!
上の写真では、ザーっと羅列してプログラムを並べました。
4,5歳児クラスの場合はこの方法を使うことが多かったです。
なぜかというと、今すべきことはもちろん、「次にあること」が分かるので、
活動の見通しが付くからです。
もしも、この自作のプログラムを見ていない子どもがいたとしても、
気に掛けて見ている子どもは必ずいます。
「あ!次はリレーの準備をしなきゃ!」と声を上げてくれるんです(^^)
2,3歳児のクラスでは、1プログラム1枚という方法もあります。
終わったら、めくる。
終わったら、めくる。。。
そうすると、子どもたちには「今」が分かりやすいですね。
もちろん、小さな子どもたちにも、先を見通せる手立ては必要です。
例えば、「(今している)大きい組さんのリレーが終わったら、みんなはダンスの服を着ようね!」
とちょっと声掛けしておくだけで、次への切り替えも変わってきます(^^)
支援を要する子どもへの配慮
[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”kokko.png” name=”こっこ先生”]先輩先生!一番見てほしかった、○○ちゃん(支援を要する子ども)が全然プログラムを見ていませんでした。目に入らない、と言った感じで・・・[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”senpai-speech.png” name=”先輩先生”]どんな風に作るとその子にピッタリくるのか、事前にこちらが試行錯誤をする必要があるわね。[/speech_bubble]
個に応じた支援グッズを!
クラスみんなが見れるプログラムと、その子専用のプログラムを分けて作っておくこともいいかもしれませんね。
「自分のもの°˖✧」というのは子どもにとっては嬉しいものです(^^)
事前に渡しておいて、使い方を知らせます。
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”senpai-speech.png” name=”先輩先生”]「使い方を知らせる」って意外と大事☝いろいろグッズを作っても、子どもが使えていなかったら意味がないからね![/speech_bubble]
[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”kokko.png” name=”こっこ先生”]保護者の方へもこんなグッズを使ってみようと思うんですがいかがですか、と一声掛けておくといいですよね![/speech_bubble]
支援を要する子どもには様々な特性がありますから、「その子が興味を持っていること」「好きなもの」などをグッズに取り入れましょう。
・文字に興味を持っている子
・写真があると理解しやすい子
・好きなキャラクターがある子 などなど
それをグッズに生かすことで、子どもは興味を持ちやすくなります。
じゃあ、どんな風に形にしていくか・・・
●数字部分を目立たせる。
→数字をめくるとプログラム名が出てくる仕掛けを作る。
→本のようにして「次は○(数字)ページだよ」と声掛けをする。 などの工夫も👍
●プログラム順に写真を見せる。
→ラミネートをかけてカード式にする。
→リングを通して、めくれるようにする。 などの工夫も👍
●自分の出るプログラムに好きなキャラクターを登場させる。
→キャラクターの絵を描いておく。
→プログラム終了後にごほうびとしてキャラクターのシールを貼る。 などの工夫も👍
気を付けたいこと!見落としがちな注意点。
その子の特性に合ったグッズ作り!考えているとつい、情報が盛りだくさんになってしまうことがあります。
[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”kokko.png” name=”こっこ先生”]「これも知らせたい!」
「あれも知らせたい!」
「あ、ここではトイレに行っておいたほうが・・・」[/speech_bubble]
と、いう感じです(^^;)
でもこれ、
「必要な情報を自分で選ぶ」ことが苦手な子どもにとっては、本当に大事なことがなんなのか分かりにくいグッズになりかねません。
支援グッズの本来のねらいは何か。
支援グッズはなんのために使うのか、というと。
必要最低限の情報を
個に応じた方法で
分かりやすく伝えるもの。
そして、そのグッズがあることによって
見通しがつき、
意欲が持てるようになることで、
行事に楽しんで参加できること。
をねらっています。
子どもたちのために、できることは!?
これまで、いろいろな事例を挙げてきましたが、みなさんの担当をしている子どもの実態は?
困っていることは?
興味のあることは?
そんなことを整理していくと、必要な支援や保育教材が見えてくるのではないかと思います。
[speech_bubble type=”std” subtype=”R1″ icon=”kokko.png” name=”こっこ先生”]先輩に聞きながら進めていくことも大切ですね♪[/speech_bubble]
[speech_bubble type=”std” subtype=”L1″ icon=”senpai-speech.png” name=”先輩先生”]若手の先生のアイディアには、感心させられるわ♡うちのクラスもそろえて作ってみようかしら![/speech_bubble]
園やクラスの足並みをそろえることも大事ですからね♪
先生方、そして子どもたちが笑顔で運動会を迎えられますように(*’ω’*)
陰ながら、応援しています!
それではみなさん、さようなら🐣


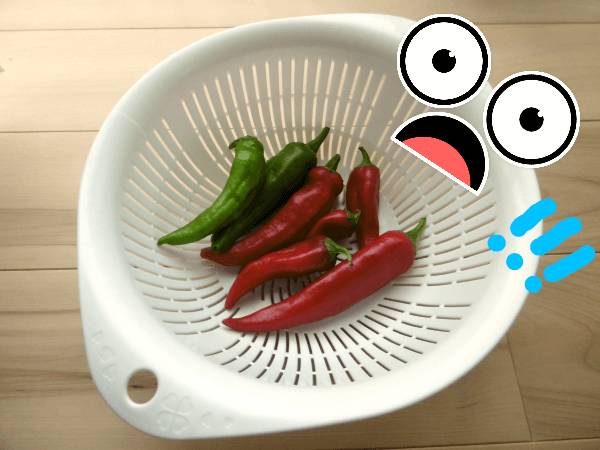

コメント